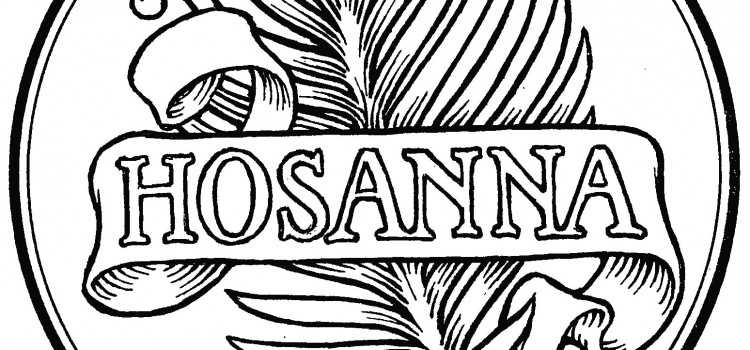聖書のこの記事の背景にはあの 有名なサロメとヨハネの話があります
洗礼者ヨハネが殺害された。
それは イエスご自身にとっても ショッキング事件だったことは 間違いありません。
そこで イエスは 人里離れたところに一人で行き、父なる神との対話を
試みようとしたのではと、思われます。
しかし 群集はそれを見て イエスの後を追うことになります。
そこで この5,000人への食事提供の話が起こるのです
ここでは イエスと弟子との距離があります
よく読むと イエスは弟子たちを突き放しているようにも思えます
5千人への給食の記事はどの福音書にも見られます。
しかも、ルカをのぞいては「湖の上を歩くイエス」の記事が続いています。
マルコによる福音書では、パンの出来事と結び付けいます。8:14
マタイによる福音書では、ペテロの信仰告白と結び付けています。16:13
ルカによる福音書では 5千人の給食の後に信仰告白が来ています。9:13
ヨハネによる福音書では この記事の少し後に
信仰告白が記されています。 6:9
聖書はこの5000人への食事提供の生地の後に信仰告白が結びついています。
ここで イエスはなぜ この時に弟子たちとの距離を取っているのでしょうか。
それは、イエスは弟子達を意図的突き放しているように感じます。
そこには 目的があり、現代流に言えば「体験学習」をさせているように理解できます。
14章全体を弟子達への教育的な配慮、体験学習と見ると、そのイエスの意図はどこにあるのかと思います
この出来事の前に起こった、洗礼者ヨハネの殺害はイエスに取っては死を予感する出来事であったに違いありません。
いつかは、弟子達を残して去っていくことになる。そのとき、自分が、いつも弟子達と共にいて、弟子達に命の糧を与えるという事を悟らせなければならない。その事のしらすための いわば体験学習であったのではと思わせられます。
さて
私たちの主日礼拝とはどのような順序な内容によって形づけられているのでしょうか。それは 礼拝全体が主の福音を証し、それを体験するように考えられています。「悔い改めで福音を信ずる」という事からはじまります。
そして、説教を聞き、その後で信仰告白をします。そして自分を神に捧げる、奉献、聖餐と続きます。この聖餐を受ける前には信仰告白がどうしても必要です。キリストを神の独り子と信じ、その救いの業の恵みを具体的にこの身体に受ける。自分の中に、具体的にキリストが入って下さる。その体験と、その現実が聖餐毎に起こります。教会の歴史的信仰告白である、信仰告白は二ケア信条・使徒信条が使われていますが、根源的には あの、ペテロの信仰告白です。
私たちは信仰告白をし、神の恩寵、神の恵みの救いに入る実感をあの聖餐で受けることができます。
この与えられた恵みに甘んじることなく、謙虚に受け止め、共に主の食卓に連なるものとなりたい。